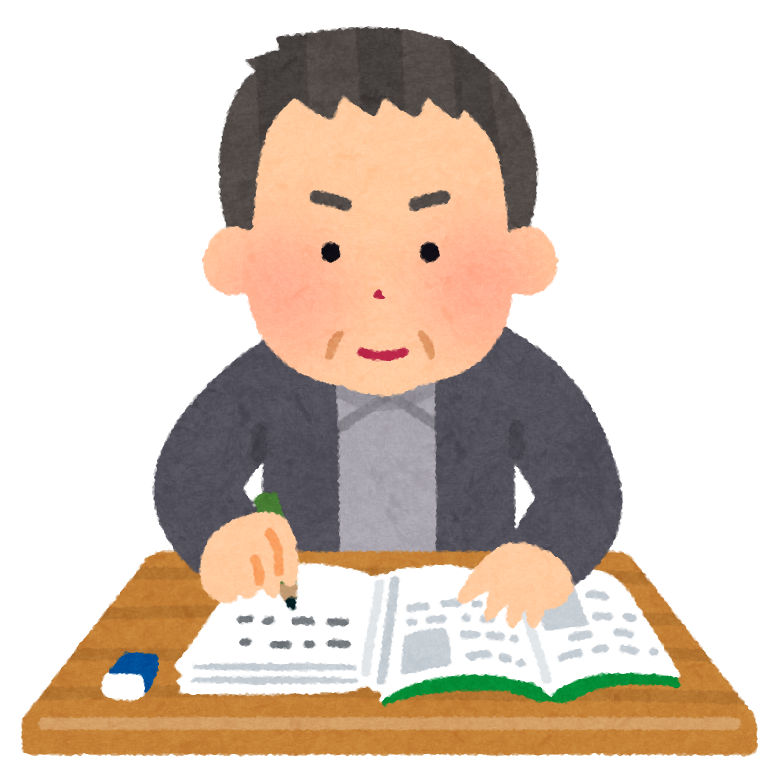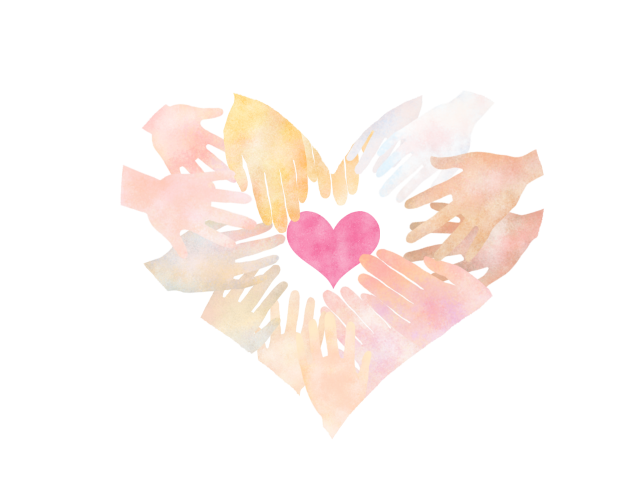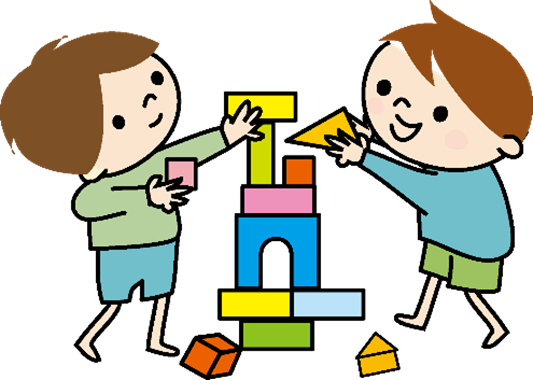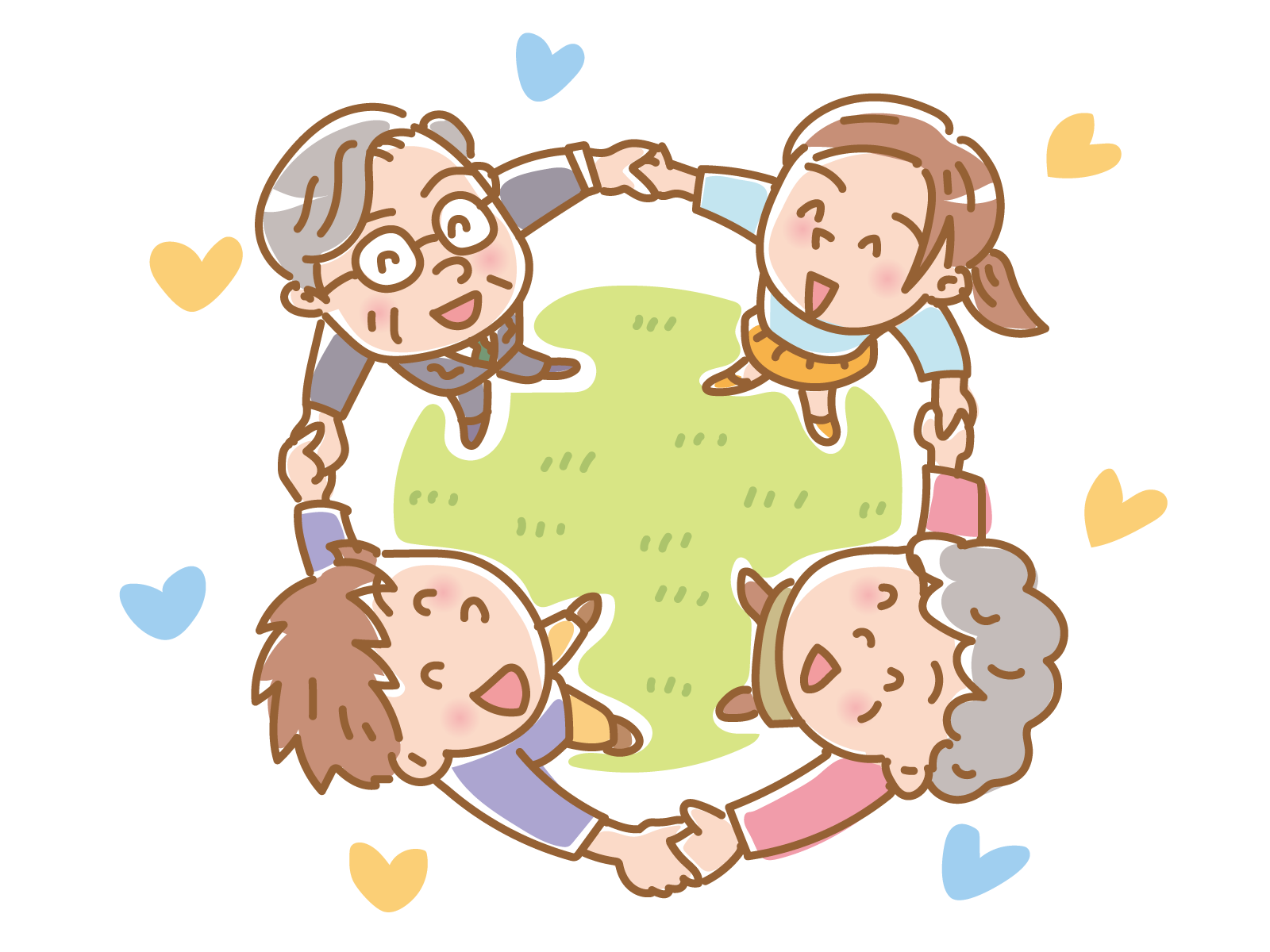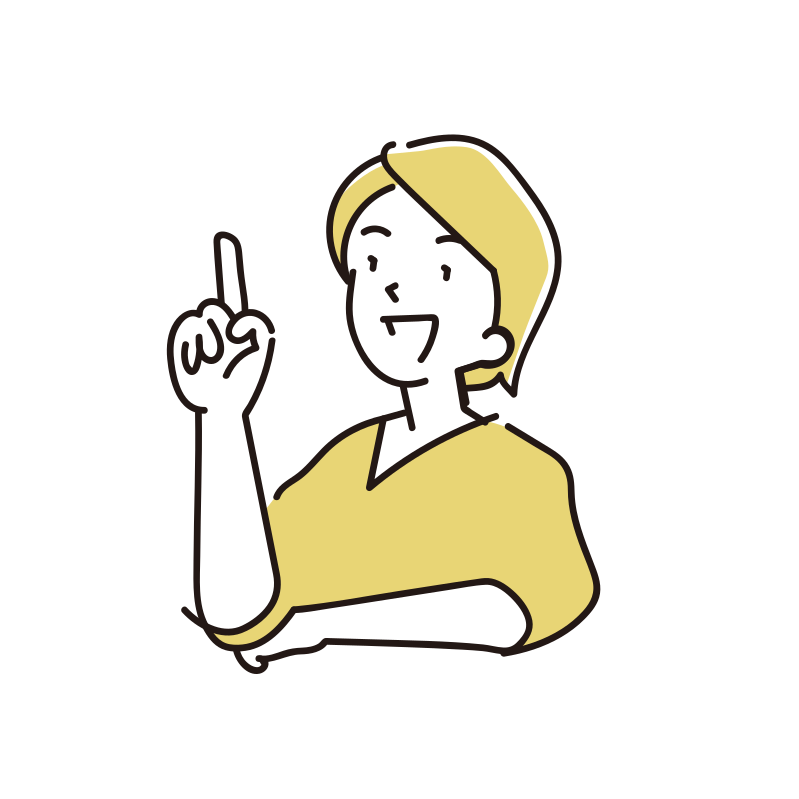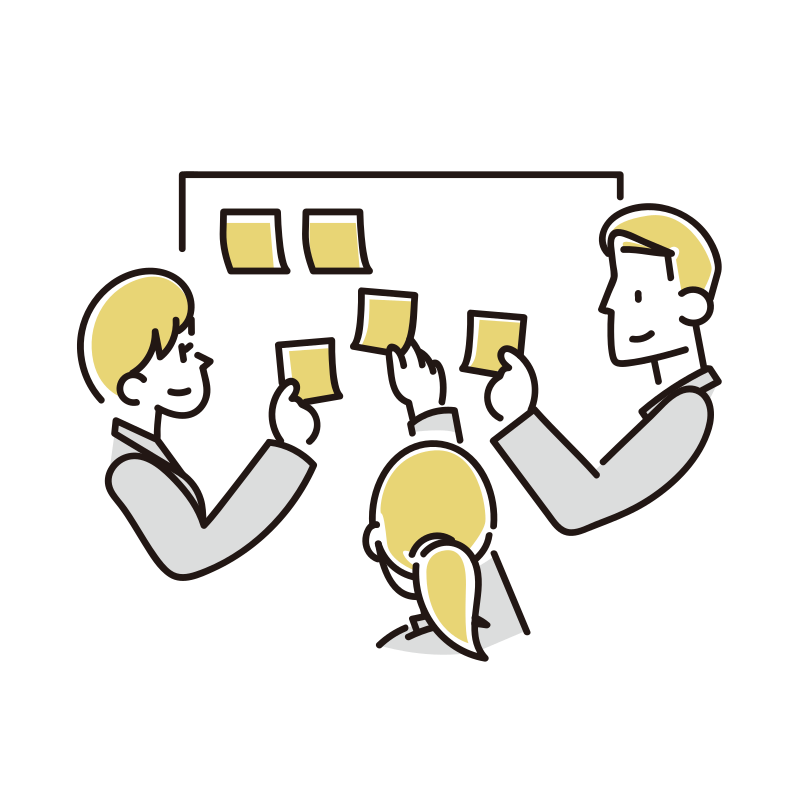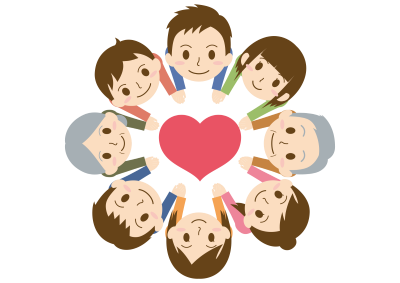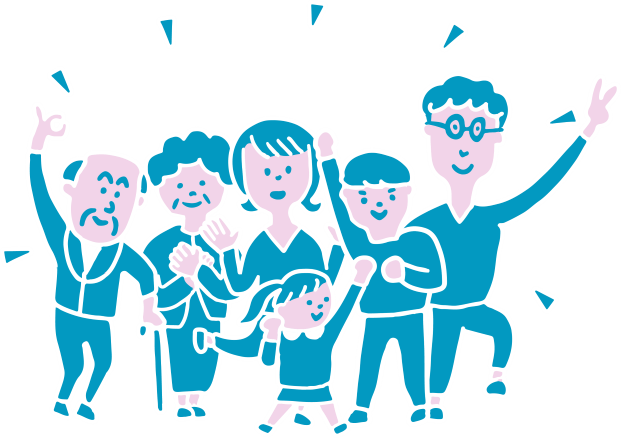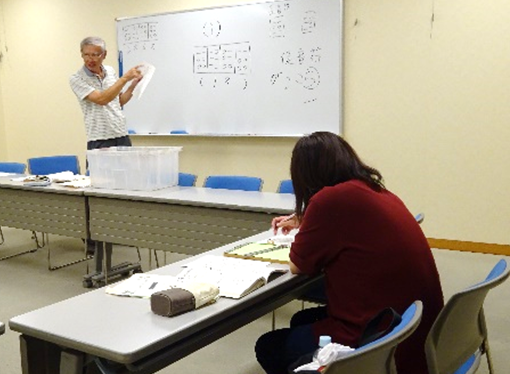毎年、10月1日から翌年3月31日まで赤い羽根共同募金運動が全国で実施されています。その一環で行う12月1日から31日までの歳末たすけあい運動も併せて、地域の皆様よりたくさんのご協力をいただきました。皆様のご理解・ご協力に改めて感謝を申し上げます。
街頭募金活動も行い、民生委員さんや市内の中高生、福祉団体等に豊橋駅周辺での募金活動にご参加いただきました。ある日、私も中高生と一緒に立たせていただいたところ、白杖を持った方がお一人で通りかかったため、お手伝いすることはないか声をかけさせてもらいました。「点字ブロックを通れるから大丈夫、ありがとう」と仰るので、「お気をつけて」と見送ったのですが、少し経ってからその方が戻ってこられ、私を探して募金を渡してくださったのです。視覚障害があり、私たちが募金活動をしていると見て分かることはできなかったと思うのですが、一度離れてからでも私たちの声に気付いてお気持ちをくださったのだと思うと、とてもありがたく印象深い出来事でした。活動に参加した中高生も自ら募金をしてくれたり、お出かけされる中で皆様が足を止めてくださったり、募金一つ一つのありがたみを感じます。
そうして集めさせていただく募金ですが、使途についても少しお話ししたいと思います。本会でいただいたお金は一度愛知県共同募金会へ送金し、配分委員会を経て、県内の社会福祉協議会や福祉施設・団体等へ配分されます。本会ではその配分金を、障害者等福祉団体や民生委員児童委員協議会活動、ボランティア活動、子育て支援事業等への助成、敬老の日の祝品配布や、子どもの施設・事業所への義援金贈呈等に役立てています。また、災害発生時には緊急支援、復旧支援活動にも活用されており、皆様のご協力が本当に様々な地域福祉向上のための大きな支えになっております。
より詳しい情報が『赤い羽根データベースはねっと』(https://hanett.akaihane.or.jp)でご覧いただけますので、ご関心を向けていただけますと幸いです。